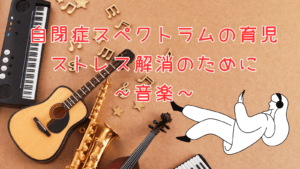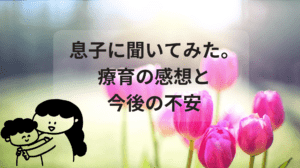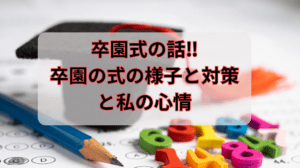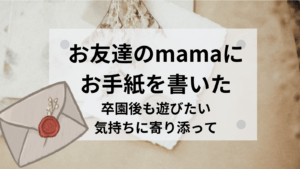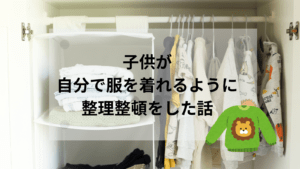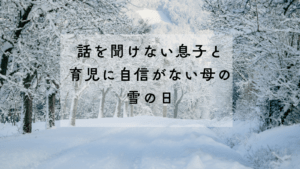自閉症スペクトラムの子どもの育児をするにあたり、母親は特に強いストレスがかかることが予測されます。
そのストレスを緩和させるための手段として「睡眠」を選択しました!!
<この記事をおすすめする人>
自閉症スペクトラムの子どもを育てている人
ストレスを発散したいと考えている人
睡眠でストレスを発散させたいと思っている人
ストレスは抱え込みすぎて心身を壊さないようにうまく付き合っていく必要がありますよね。
その時に調べたストレス解消方法です。

ストレス解消の一つの睡眠!
よく寝るために
・ぬるめのお風呂・α波がでる音楽・朝日を浴びる
・睡眠環境の見直し(室温・寝具など)
・入院前にしてはいけないことに注意して
良質な睡眠を意識!
明日の育児に備えましょう🥺
睡眠

睡眠には色々な効果が言われています。
その一つが、うつ状態になるリスクを軽減です。また、生活習慣病や寿命に関係するような病気の発症リスクも軽減してくれると言われています。
人によって最適な睡眠時間は違うと思いますが、6時間以上の睡眠をとると日中の疲労感やストレスを軽減できると言われています。
良質な睡眠をとるために
良質な睡眠をとるためには寝る前に交感神経を休ませ、副交感神経を優位にさせ穏やかな気持ちになることが大切です。
交感神経が優位になる状況は簡単にいうと、遠足の前日みたいなドキドキして眠れないという状況、興奮している状態ですね。
では寝る前に必要な副交感神経を優位にさせるためには,どんな方法があるでしょう。
簡単にできるのは3つ
➀ぬるめのお風呂
②眠りを誘う音楽を聴く
③朝日をあびることです。
ぬるめのお風呂

お風呂のお湯の温度はどのくらいでいつも入っていますか?
お風呂で副交感神経を優位にするためには温度は高すぎない方がいいといいます。
37~39度と少しぬるめのお湯に入り、
自分のお気に入りの入浴剤を入れてゆっくりお風呂にはいることがおススメです。
眠りを誘う音楽を聴く
人はリラックスをする時に脳からα波という脳波が出ると言われています。α波はストレス解消にもよいのです。ではα波を誘発する音楽は高周波の音楽です。

クラシック音楽ではモーツアルトの楽曲などα波が出やすいと言われています。音楽の音以外には自然の音を聴くことも大切です。川のせせらぎ、風の音などはリラックス効果が大きくα波が出やすいと言われています。
朝日をあびる
朝日を浴びることでメラトニンというホルモンが増加するので、良質な睡眠をとるために朝起きたらしっかりとカーテンを開けて日を浴びてほしいと思います。朝日を浴びて体内時計を整えましょう。
睡眠環境

寝室の気温と湿度
寝室の気温も重要です。夏場は26度前後 冬場は16度前後、湿度は50%程度が理想と言われています。個人の体感温度は異なるのであくまで理想とのことです。
明るさ
寝室の明るさは1~30ルクス程度がいいと言われています。どの程度の明るさというとロウソクを灯した明るさ以上街灯の明るさ以下というイメージです。また、寝る1~2時間前には部屋の明るさを気持ち暗くすると睡眠の導入がしやすいです。

真っ暗で寝る方もいますが、不安を感じ寝付けずに交感神経が活性化してしまう可能性もあるので注意が必要です。
マットレス・敷布団の硬さ・枕の高さ
マットレスは柔らかすぎると腰に負担がかかったり、硬すぎるとお尻や背中が圧迫されます。実際に横になって自分の体型や好みに合ったものを選ぶことが大切です。枕も高すぎたり、低すぎたりするとストレスが掛かりますので、横に寝た際に立っている姿勢に近くなるものを選ぶと眠りやすくなります。
睡眠前に控えること

飲食について
睡眠2時間前までに食事を終わると消化器官への負担があります。逆に寝る直前などに食事をすると胃や腸が働くため睡眠をするための身体の準備が整いにくいです。また、コーヒーなどカフェインを含むものは覚醒作用があります。カフェインは栄養ドリンクなどにも含まれるので、しっかり寝たい時は控える方がいい睡眠につながります。
スマホの画面を見る

寝る前にスマホの画面をみることはブルーライトがメラトニンの分泌に影響を与えるため寝つきが悪くなると言われています。体内時計を調整しているメラトニンの分泌が低下すると眠りが浅くなり、結果、睡眠のリズムが崩れるので朝起きるのが辛くなることもあります。脳が勘違いしないためにも寝る前にスマホの操作は控えるのがよいです。
激しい運動
息が切れるような激しい運動は、交感神経が刺激されるため入眠を妨げてしまいます。

どうしても激しい筋トレやランニングなどを行いたい場合は食事後1~2時間が血糖の上昇を抑制することができる面からもおススメと言えます。
お昼寝の効果

お昼寝をすることでもストレスの解消に繋がると言われています。お昼寝は午睡とも言われ、午後の業務効率の改善や疲労の回復、集中力や記憶力の向上に効果があると言われています。また、精神的な安定にもつながり、心身をリラックスすることができます。
理想的なお昼寝
お昼寝は15~20分の短時間とし、午後3時までにすることで目覚めもよく作業効率も向上します。30分以上のお昼寝は夜の睡眠に影響を与えることや逆に疲労感を感じてしまう可能性もあるため、お昼寝をする際には、タイミングと時間に注意する必要があります。
睡眠をして母の回復を
発達障害児の育児をしているとストレスが溜まります。睡眠はしっかりとりましょうと言っても。子ども自体がなかなか寝なかったり、ゆっくりお風呂に入りましょうといっても、子どもと入らなきゃならないのにってゆっくりってどういうことだとなります。いや。私がなりました。

お昼寝もなかなかしない場合は、もう子供と一緒に9時くらいに寝てしまうつもりで動いた方が心身が休まります。
まとめ

自分のストレス解消のための睡眠は、夜の睡眠を快適にするために、
睡眠環境を見直したり、睡眠前の行動にも注意する必要があります。
睡眠のための儀式を用いて、音楽を聴いたり、朝日を浴びたり、ぬるめのお風呂に入ってリラックス✨
副交感神経が優位になる行動をしていきましょう。
子どもの睡眠障害は主治医に相談しながら、自宅でできる工夫をして、
子どもの入眠前ルーティンを決めてお母さんもゆっくり休みましょ😆