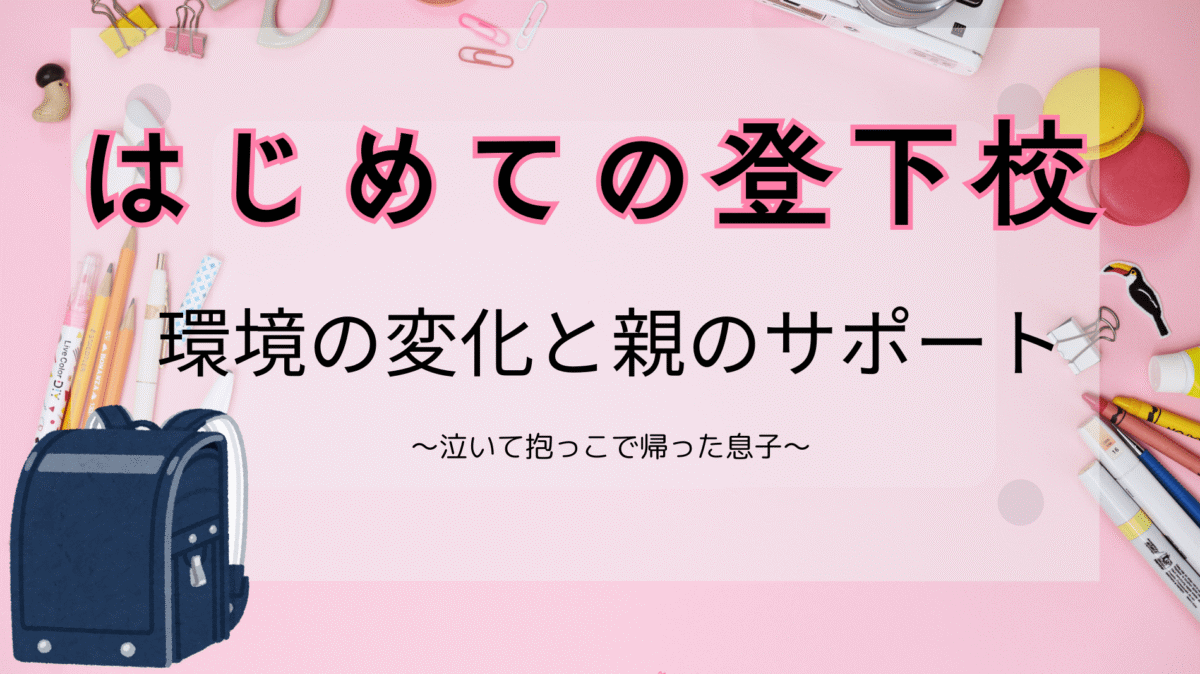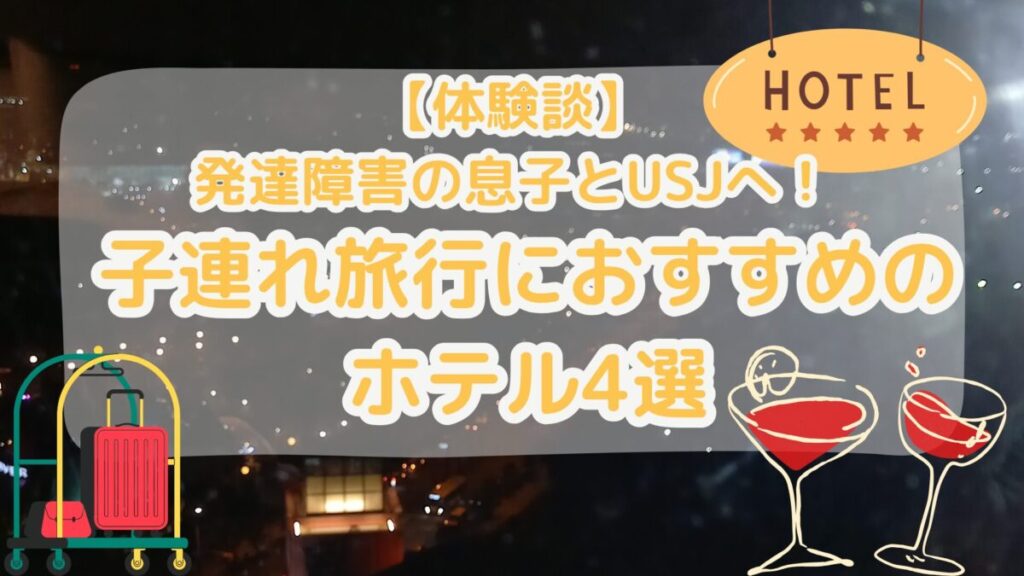今回の記事は
自閉症スペクトラムの息子が
初めての登下校の一日について綴ります。
行きはなんとかお兄さん、お姉さんと行けたものの、
帰りは予想外の展開に…。
当日の様子と親としての気持ち、
準備をしておいてよかったこと、
今後に向けた工夫・気持ちの受け止め方。
同じように不安や戸惑いを感じている方に
安心を届けられたらと思います。

大切だったのは、
集団登校とは何かを説明しながらの事前の準備と
下校など準備できないことに対して、
「こうなるかもしれない」という想定外に対応する
親の気持ちでした。
<おすすめの人>
・自閉症スペクトラムのお子さんを育てている方
・発達障害のお子さんを支援している方
・特別支援教育に関わる方
・自閉症スペクトラムについて学びたい方
初めての集団登校、事前準備のポイント
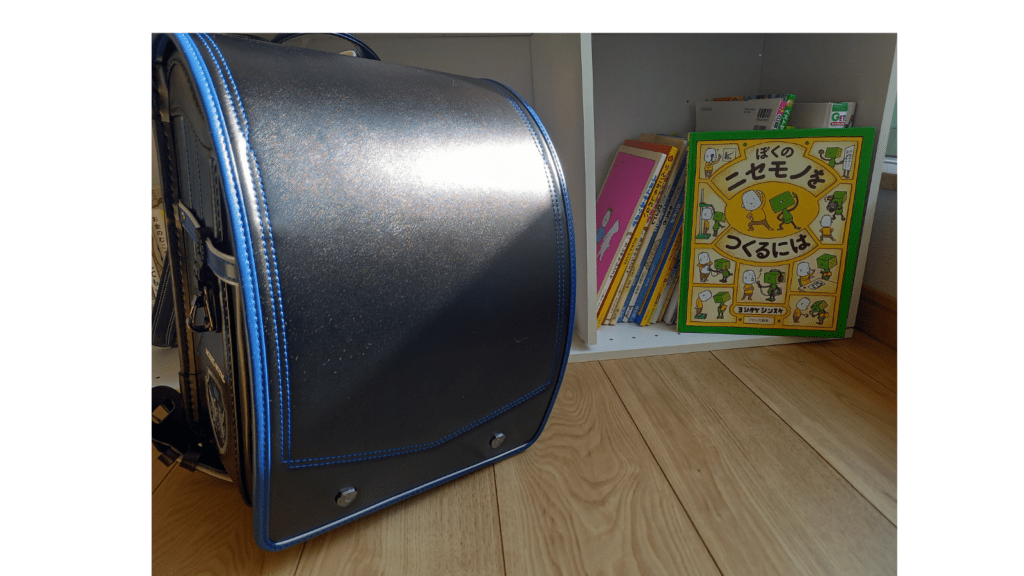
初めての登下校は、子供も親もドキドキします。
特に自閉症スペクトラムの特性を持つ子供にとって
「慣れない環境」「いつもと違う」ことはとてもストレスになります。
なので、事前の準備がとても大切です。
ランドセルを背負って息子と登校道を確認
入学の1週間前、
実際に自宅からランドセルにノートと本を数冊入れて実際の登校道を歩きました。

「集合場所で6年生が待っているよ」と話、
「お兄さんの後ろに並んで歩いて行くよ」と
集団登校の説明して、出発です。
ですが、自宅から300mほど歩いたところで、
「重い…。ママもって…。」と。
「小学校はこれより重いのよ」と話をしながらなんとか1キロ歩きました。
歩道の縁石を歩いたり、
先が見えにくいカーブだったりを危ない様子もみられたので、
注意し、途中まで一緒に登校するので、見送るポイントの場所を伝えました。
その後は、「小学校は行ったら持つから、あとはママもって!!」と
ランドセルを道路の真ん中に放置して、
学校に向かって走り出しました。
「走らない‼」と
私も大きな声を上げながら学校まで小走りでついて行きます。
学校についたら一年生の玄関を確認し、
校庭で遊んで帰りました。
帰宅後、歩いた道を手描きの地図で振り返り。
カレンダーをみながら、
この日まではここまで一緒に行くからねと話をしました。
登下校のポイントを整理
登校の準備でしたことは、
➀登校道を一緒にランドセルを背負って歩く
②集合場所と集団登校とはどんなものかを説明する
③見送るポイントを伝える
④玄関の位置を確認する
➄地図で道を振り返り、見送るポイントを再度伝えるです。
小学校までの道のりは、近くに公園があるので、
何回か歩いて公園にいったこともありました。
ランドセルを背負って歩いたのはもう一回する?と
子供に聞くとわかったから大丈夫と言われたので、一回だけでした。
一回でもしといてよかったと思いました。

息子は当日の登校で、
約束の曲がり角まで行くとスムーズに集団登校ができたのです。
私も、思ったよりスムーズに行けたなと一安心しました。
練習できない下校の様子をみて、登校は練習してよかったと感じました…。
初登校の帰り道、環境の変化に戸惑う息子

自閉症スペクトラムの子どもは、
予定通りに進むことで安心ができます。
しかし、
下校初日は環境の変化と周囲の騒がしさ、
先生のバタバタした様子などの不確定な要素が多く
息子にとってはとてもストレスがかかる状況でした。
お迎えの時間は11時40分だったので、
その前に近所のママさんたちと学校へ向かいました。
一年生の玄関前には、
整列できていない子供たちが100人近くいます。
それはもう、がやがやしており、集団下校なので帰る方向別に、
先生が子供たちを列に誘導しています。
まだ先生たちも名前と顔の一致が難しいようで、
下校の集団を作るのに苦労をしているようでした。
抱っこで1.2キロを帰宅!親としての思いと気づき
息子はとても不安定でした。
高いところに登ったり、校庭を走り回ったり、
抱っこと甘えたり、みんな並んでいるのに
一緒に整列することができず、最後には泣いてしまいました。
そんな状態で「歩いて」と話してももちろん無理で、
私はランドセルと22キロの息子を抱っこして、
自宅までの1.2キロを抱っこして帰りました。
抱っこしながらの帰り道。
重かったけれど、
重たさ以上に息子の気持ちを受け止めなきゃという思いで胸がいっぱいでした。

「大丈夫だよ」「大丈夫だよ」って
一先ず息子に安心してほしい気持ちでいっぱいでした。
「おうち帰ったら、アイス食べようね」
「すごく頑張ったね」と
とにかく学校に行けてよかった
それだけで100点だと。
たくさん褒めました。

でも、私の心の中では、
「この子は明日は大丈夫だろうか。
学校に行けるかな?」との思いもあり、
子供に悟られないように、
自分の気持ちも落ち着くように必死でした。
事前準備と想定外に対する対応
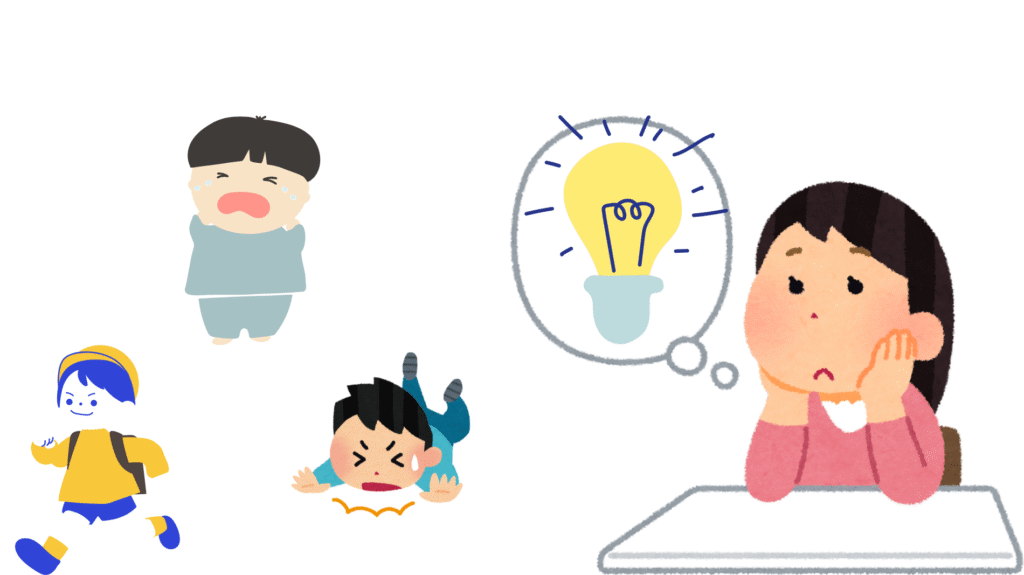
朝の登校は事前に、
どこが集合場所か、誰と行くか、
実際に登校する道をランドセルを背負って一緒に歩きました。
母はここまで一緒に行くからねと声をかけ、
自宅でも地図を書いてここまでは一緒に行くよと確認を重ねました。
それがよかったのか、
決まったポイントでお別れしてもぐずりもせずに登校してくれました。
近所の3年生のお姉さんが名前を憶えてくれて、
一度公園で遊んだこともよかったのだと思います。
事前準備が大事だなと実感をしました。
また、想定外を受け入れる柔軟さも母には必要です。
難しいですよね。
事前にこんな風になるかもと思っている
3段階くらい上の状況を想像しておくとまだ、
穏やかな気持ちでいられると思います。

子供が安心できる環境をどう整えるか、
そして上手くいかなかった時、
親はどのように対応するか。
そして、どのように心を保つか。
それが大切だなと感じました
まとめ
子どもの集団登校に行くまでに3つの準備をしました。
- 入学前にランドセルを背負って実際の登校ルートを一緒に歩く
- 集団登校の説明と見送りポイントを明確に
- 手描きの地図やカレンダーで「見通し」を共有
この準備により、息子は当日も約束のポイントまで落ち着いて登校。
不安が強くなりがちな新しい環境でも、
「見える化」と予習が安心を支えてくれました。
ですが、下校は予想外の展開になり、
抱っこしながらの帰り道は、親として気持ちを受け止める時間でもありました。

「安心できる環境をどう整えるか」
「うまくいかないとき、どう受け止めるか」
「親自身の心をどう保つか」…子どもの成長を支えるには、親の柔軟さと深呼吸も大切だと改めて感じました。
同じように不安や戸惑いを感じているご家庭に、
少しでも「わかる」「うちもそうだった」と思ってもらえたら嬉しいです。
たった一日でも、子どもにとっては大きな冒険。
一歩一歩、寄り添いながら一緒に進んでいきましょう。
登校初日は子どもにとっても
親にとっても感情が揺さぶられる一日でした。
泣きながらの帰り道も成長の一歩です。
これからも息子と一緒に小さな成功と挑戦を積み重ねていけたらと思っています。