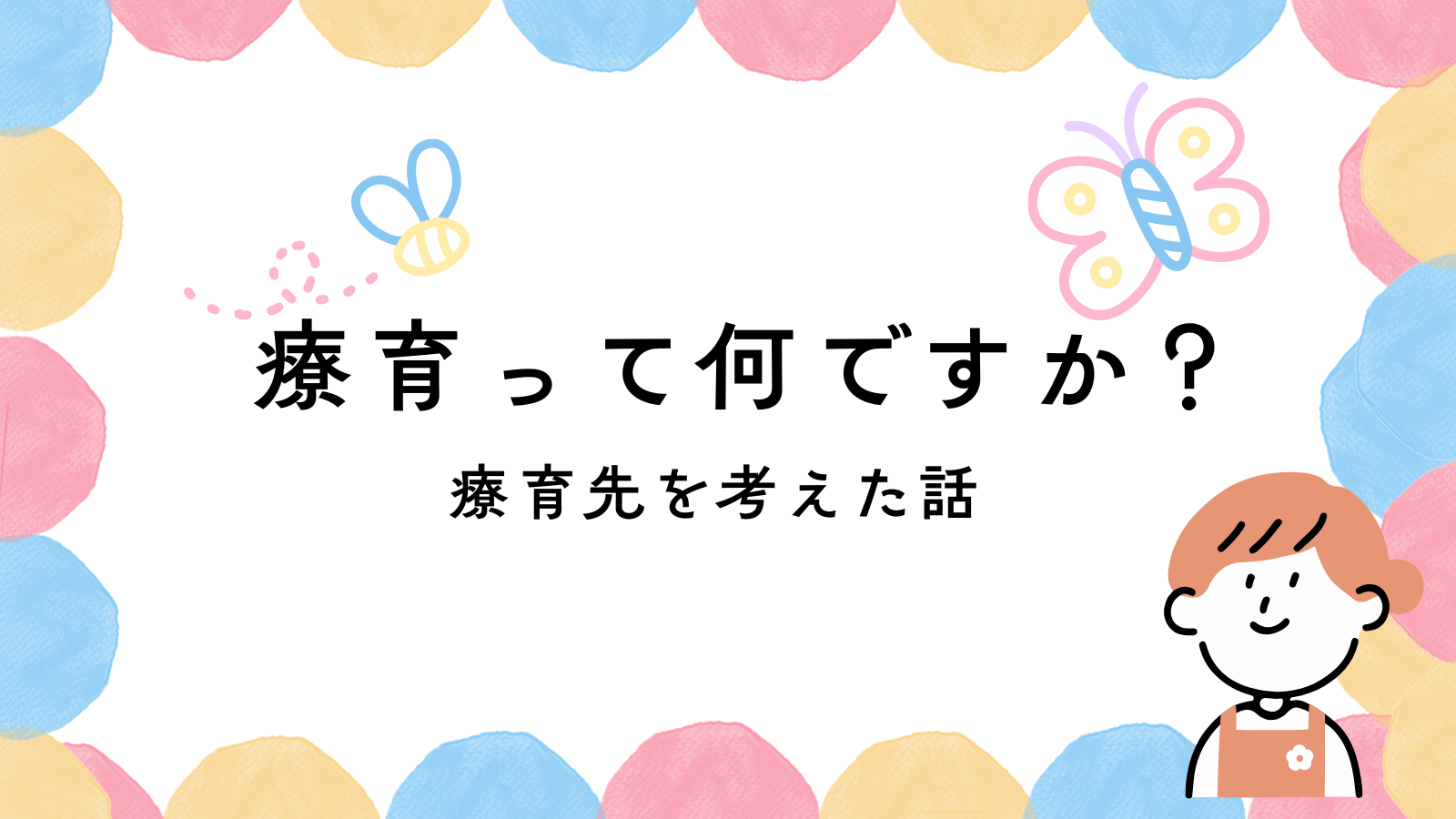「発達障害かもしれません」「グレーゾーンです」と言われたとき、
どうしたらいいのかわからなくて、すごく不安になりますよね。
私も、子どもが診断を受けたときは、「何をすればいいの?」「この子の未来はどうなるの?」って、
頭が真っ白になりました。でも、大丈夫です。ひとつずつ進めていけば、ちゃんと道は開けていきます。
この記事では、作業療法士であり、一児の母でもある私が、
療育を始めるための流れや、実際にやったことを、わかりやすくお伝えします。
私も療育にこんなにも種類があることやいろいろな事業所があることを知りませんでした。療育と言っても中身はいろいろ。調べて学んで、手続きが大変だけど、卒園した今は、私も息子も学べたことが多かったと思います
あなたの不安が、少しでも軽くなりますように。\この記事はこんな方におすすめ/
・発達障害と診断され療育を勧められた方
・グレーゾーンと言われたが療育を悩んでいる方
・「療育って何?」と疑問を感じている方
まずは自治体の福祉窓口に相談しよう
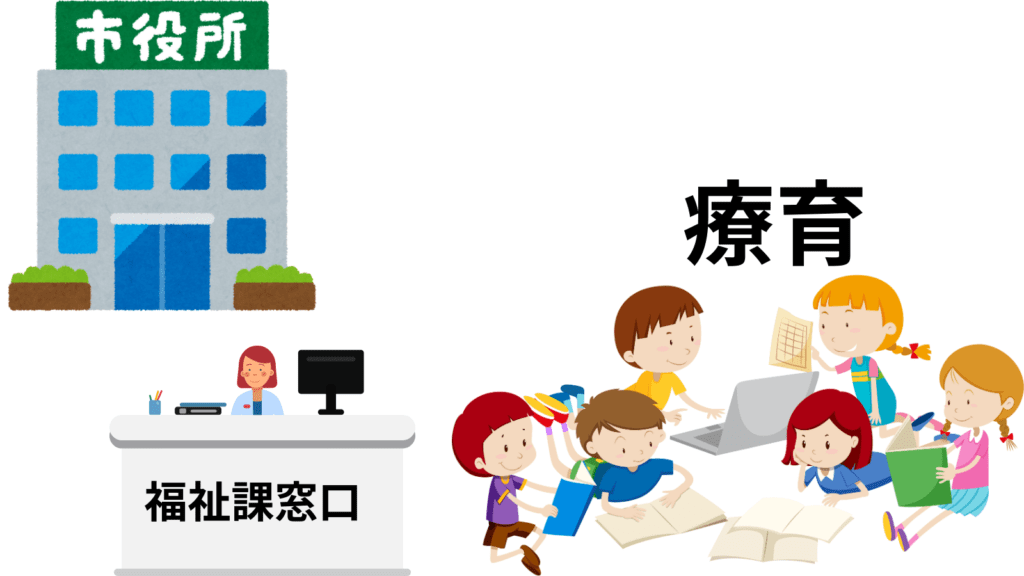
まず最初にやるべきことは、市町村の福祉窓口に相談することです。
療育(児童発達支援)を利用するためには、「通所受給者証」が必要となります。
受給者証を取得し、相談員さんを決め、療育先を探す――この流れが、療育スタートへの第一歩です。
療育とは?通うための手続きとは?
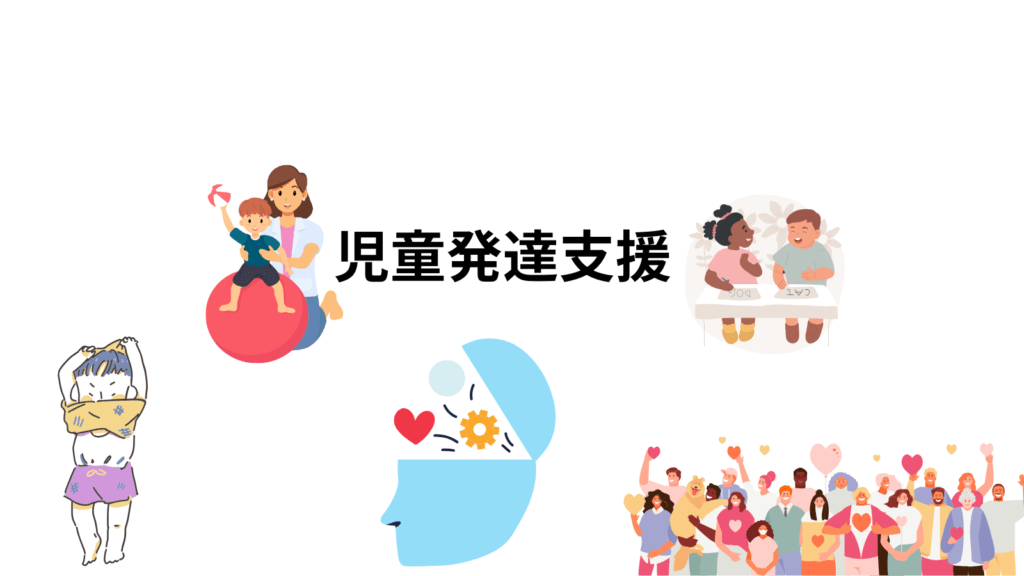
療育・児童発達支援とは?
療育とは、0〜6歳の未就学児を対象とした障害福祉サービスの一つです。
発達に課題がある子どもたちに、日常生活や社会性を身につけるための支援を行います。
費用は原則1割負担、利用には「通所受給者証」が必要です。
療育の種類
- 個別療育:マンツーマンで、苦手な分野の克服・得意分野の強化を目指します。
- 小集団療育:2~3人の小集団で、協調性や社会性を育む活動を行います。
- 集団療育:5~10人の集団で、感情コントロールや対人スキルを練習します。
- ソーシャルスキルトレーニング:社会的ルールやコミュニケーション能力を高めます。
入学前に療育を始めた我が子は集団療育にいきました。

小学校の人数が30人程度で、保育園の人数が20人程度でした。
全て療育に通うと療育先で10人だったのが、
小学校に入学するといきなり、30人の集団に入るということになるので、本人の負担になるかなと思いました。
そのため、並行通園という手段をとり、
今まで通っていた保育園と療育先に通うことにしました。
受給者証取得の手順
- 市町村の福祉窓口に相談
- 支給申請書・児童発達支援計画案・医師の意見書(診断名不要)・マイナンバー提出
- 相談員(相談支援専門員)と面談し、支援計画を作成
- 書類提出から約1か月で受給者証発行
私が実際にやったこと
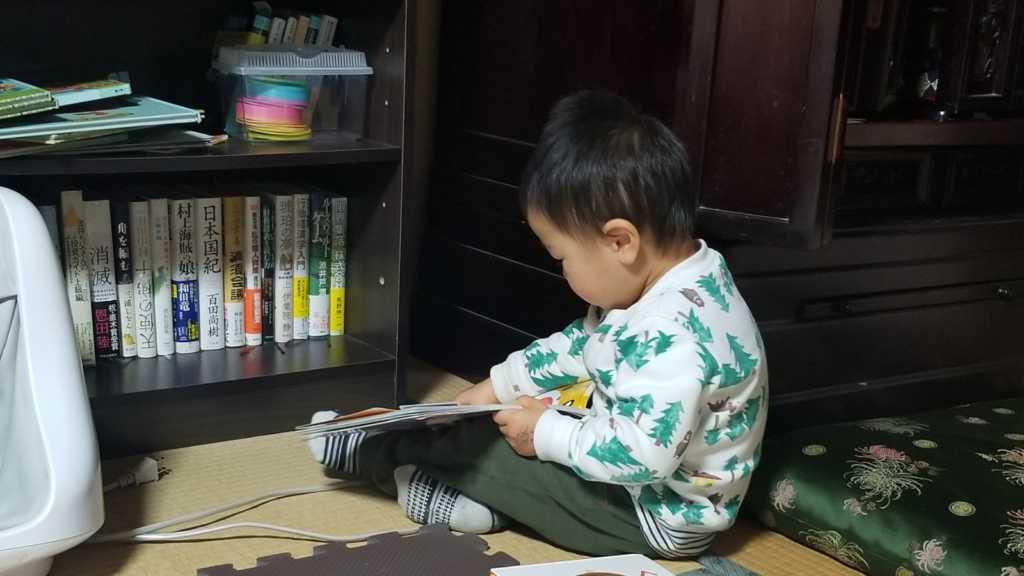
私が療育先を探し、通園を開始するまでに行ったステップは次の通りです。
- 保育園から療育を勧められる
- 市役所の福祉課に相談
- 医師に意見書を依頼
- 相談員さんと支援計画を作成
- 療育先をリサーチ(市役所一覧、WAMNET、LITALICO発達ナビなどを活用)
- 療育施設を見学・比較検討
- 通所受給者証の取得
- 療育先を決定し、並行通園スタート
その際、子どもの困りごとや保育園での様子について、何度も面談で話す必要があり、
精神的な負担も大きかったです。
電話2回(手短)、対面3回(30分以上)という頻度で、正直とても辛かった…。
でも、相談員さんや施設のスタッフが親身になって話を聞いてくれたので、何とか乗り越えられました。
こちらが、私が検索したサイトです🌞
全国の発達支援施設検索【LITALICO発達ナビ】
障害福祉サービス事業所検索 – WAM NET
療育先選びで見るべきポイント
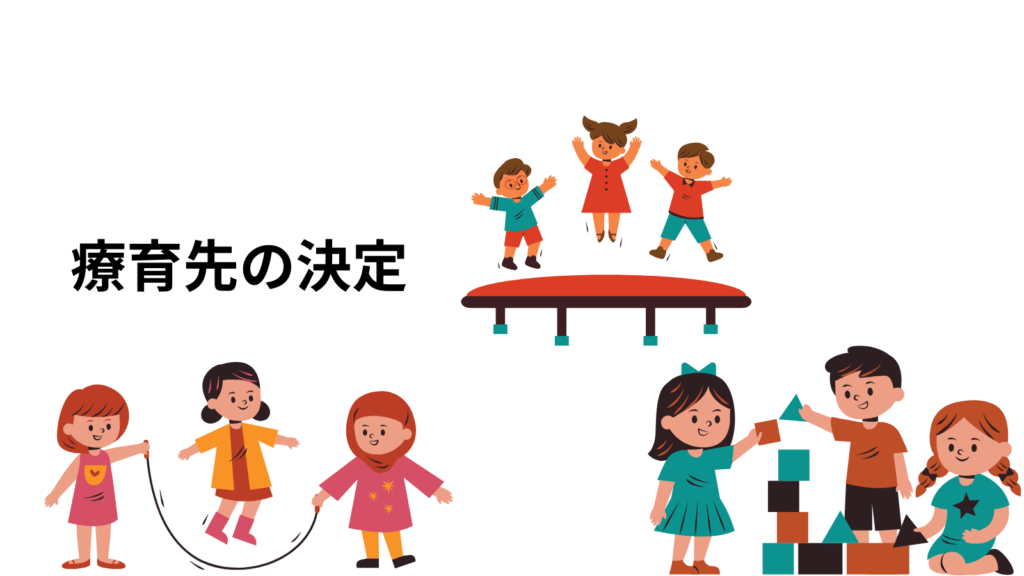
療育施設を選ぶ際には、次の点に注目しましょう。
- 通園のしやすさ:家や職場から近い?送迎バスはある?
- 子どもに合った環境か:個別療育か集団療育か、子どもの特性に合っているか
- 支援内容:身体機能・感覚統合・社会性など、何に力を入れているか
- 施設の雰囲気・専門性:スタッフの資格(作業療法士など)、経験年数、配置人数
特に「作業療法士」などの専門職が在籍しているかは一つの判断材料になりますが、経験年数や得意分野も確認するのが安心です。
見学時に「小児分野での経験は何年ですか?」と質問してみるとよいでしょう。
まとめ:

まず一歩、相談窓口に行こう
発達障害やグレーゾーンと診断され、不安な気持ちでいっぱいかもしれません。
でも、「療育に通わせたい」と思ったその気持ちが、すでに素晴らしい一歩です。
- 市町村の福祉課に相談
- 受給者証を取得
- 相談員さんと一緒に療育先を検討
- 子どもに合った療育施設に通園スタート
この流れを一つずつ進めていきましょう。
たくさんの手続きや面談があって、大変に感じるかもしれません。
それでも、子どもの未来のためにできることを着実に積み重ねていけるよう、心から応援しています。
療育とは児童発達支援の一つです。厚生労働省のガイドラインはこちらです↓