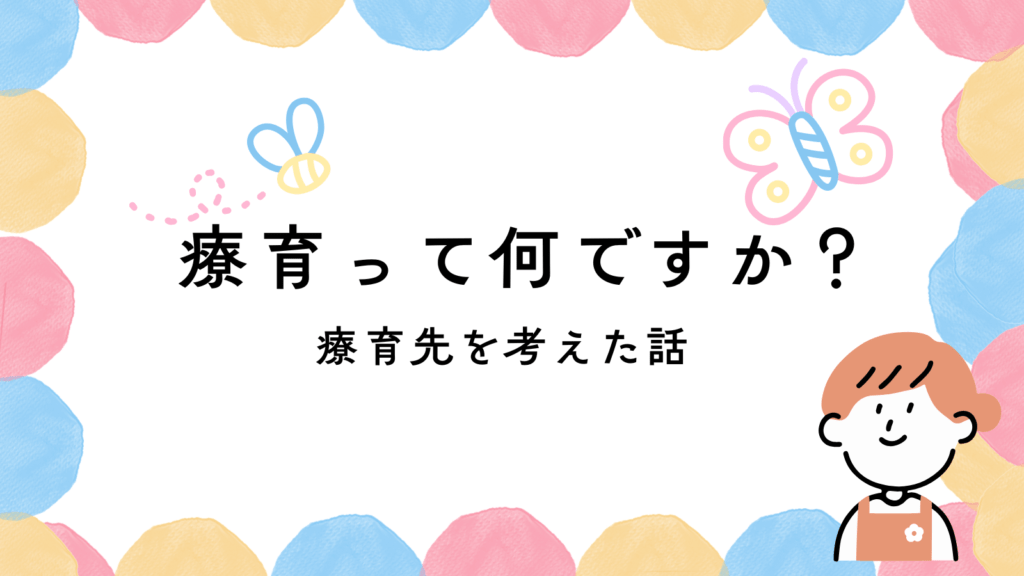自閉症スペクトラムの子どもは、
日常生活の中で
「今していること」から
「次の行動」への切り替えが苦手な傾向があります。
癇癪やぐずりが頻繁に起きると、
毎日の生活がとても大変に感じますよね。
本記事では、
作業療法士としての視点と、
実際に子育てをしてきた母親としての経験を交えながら、
切り替えがうまくいかない理由と、
我が家で効果のあった3つの対応法を紹介します。

生活の中は切り替えの連続、
それをどのように対応したらスムーズに日常が回るのか。
時間が余裕がある時は付き合うけれど、
そうもいっていられない日があるのも事実。
3つの対応を意識したら、
少しずつ子供の行動が変わってきて、
母も楽になりました。
この記事がおすすめの人
・自閉症スペクトラム子育て中の人
・子供の切り替えの難しさで悩んでいる人
・自閉症スペクトラムを支援することが ある人
息子は、生活の中で「次のこと」をするのが苦手でした。
活動をやめて「次のこと」をする時に、
癇癪を起したり、辞めるのに時間がかかったりととても大変でした。

自閉症スペクトラムと診断を受けてから、
どうしたら、生活がスムーズにいくか
作業療法士としての知識と経験を活かしながら工夫を続けてきました。
切り替えが難しい子どもへの対応で意識したいポイントは以下の3つです。
- タイミングと内容を「アナウンス」する
- 視覚的な「タイマーや砂時計」を活用する
- 「スモールステップ」で行動を小さく分ける
この3つに意識を向けることで、
子どもも安心して行動に移りやすくなり、
保護者の負担も軽減します。
切り替えが苦手な理由は「感情のコントロール」と「見通しの弱さ」
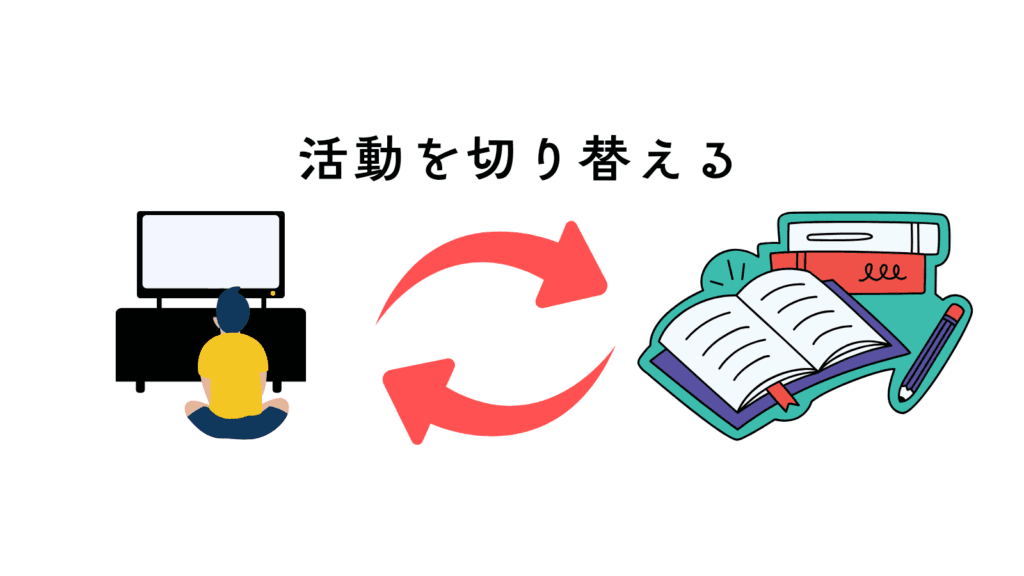
自閉症スペクトラムの子どもたちは、
自分の感情や行動をコントロールするのが苦手です。
特に「今していること」を中断して
「次にやること」に移る場面では、
癇癪やぐずりが起きやすくなります。
さらに、見通しを立てるのが苦手なことも切り替えの難しさにつながります。
「次に何をするのか」「なぜそれをするのか」がわからないままだと、
不安や抵抗感が強くなるのです。
対応①「事前アナウンス」で切り替えに安心感を
「これから何をするか」を事前に具体的に伝えることで、
子どもは安心して行動に移れます。
突然の切り替えに弱い子どもにとって、
先に見通しを伝えておくことは不安を減らす大切なサポートです。
例えば、車の中で動画を観ていた息子に対しては、
「おうちに着いたら動画はおしまい。
帰ったら手を洗って、おやつを食べようね」と伝えておきます。
そして自宅が近づいたタイミングで再度、
「あと○分でおうちだよ」と声をかけ、
家に着いた時には「好きなおやつ、食べようね」と楽しみを強調します。

アナウンスは、「いつ」「なにをするか」をセットで、何度か繰り返して伝えるのがコツです。
対応②「タイマー・砂時計」で視覚的に時間を理解

視覚的にわかる道具は、
時間の流れを把握しにくい子どもにも有効です。
数字だけのタイマーでは
時間の感覚がつかみにくい場合が多いため、
色や動きで理解できるものが向いています。
我が家では「LITALICOのねずみタイマー」や「砂時計」を活用しています。
ねずみタイマーは、
ねずみがリンゴを食べ終わるというアニメーションで
視覚的に時間の終わりが伝わりやすく、外出時にも便利です。
砂時計はいろいろな砂時計があり、
細かい時間設定ができるので、家の中での活動に向いています。

「時間が見える化」されることで、
切り替えまでの心の準備がしやすくなります。
対応③「スモールステップ」で負担を減らす
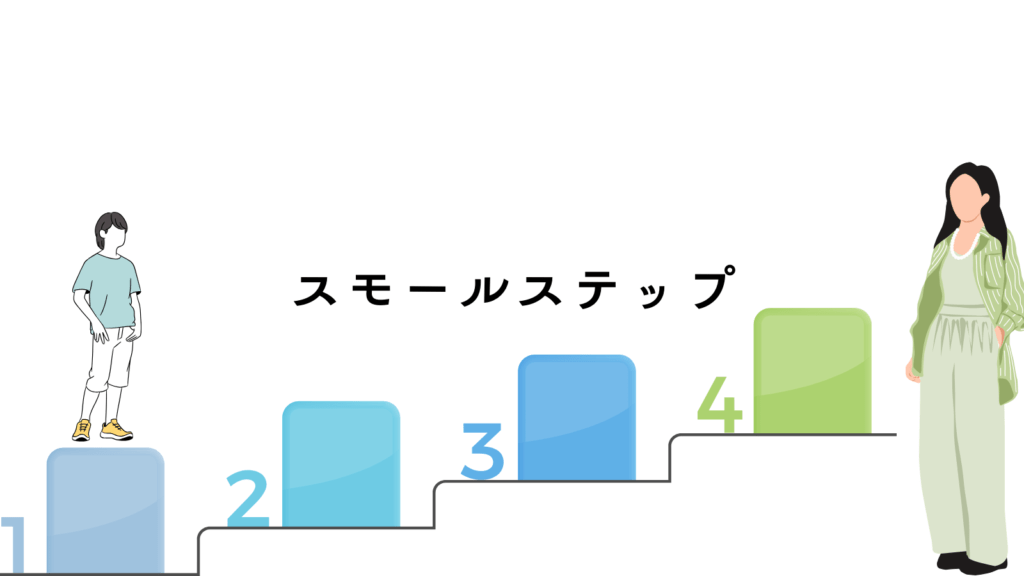
嫌な活動こそ、細かく分けて少しずつ取り組むことが大切です。
苦手なことに一気に取り組むと強い抵抗感が出てしまいます。
段階的に慣れていくことで、無理なく行動できるようになります。
お風呂が嫌いな息子には、
「湯船に入るだけ」「身体を洗うだけ」など、
選択肢を提示して選ばせていました。
できたら褒めて、徐々にステップアップ。
今日は湯船だけ、明日は身体を洗ってみよう…と、
本人のペースで進めました。

行動を「できそうな小さな一歩」に分けることが、
切り替えやすさにつながります。
まとめ:支援も育児も「できる範囲でOK」
支援の方法はたくさんあります。
でも、すべてを完璧にやる必要はありません。
私自身、登園渋りをしていた息子にスモールステップで対応しようとしても、
仕事との両立で限界を感じることが多々ありました。
大切なのは、保護者自身の心の余裕です。
子どものためにと思って無理をしすぎると、
家庭の中がしんどくなってしまいます。
できる範囲で、できる時に、少しずつ。
それだけで十分です。
今日もこの記事を読んでくれたあなたの心が、
少しでも軽くなりますように🌞
。