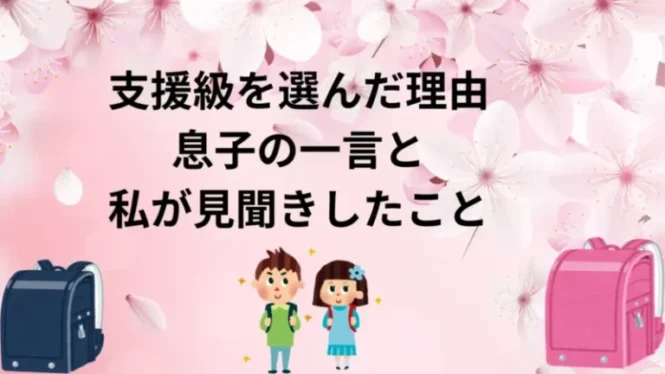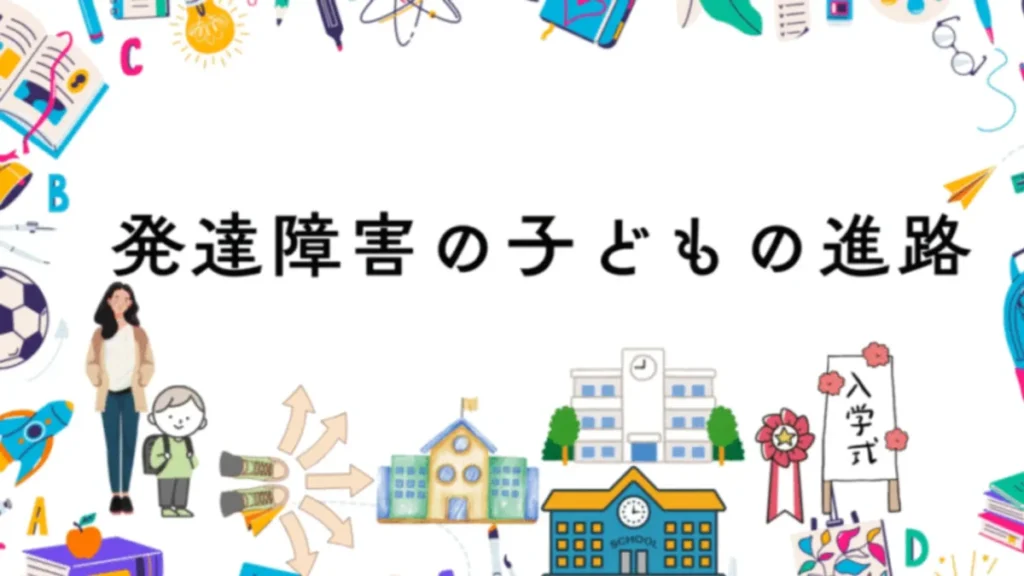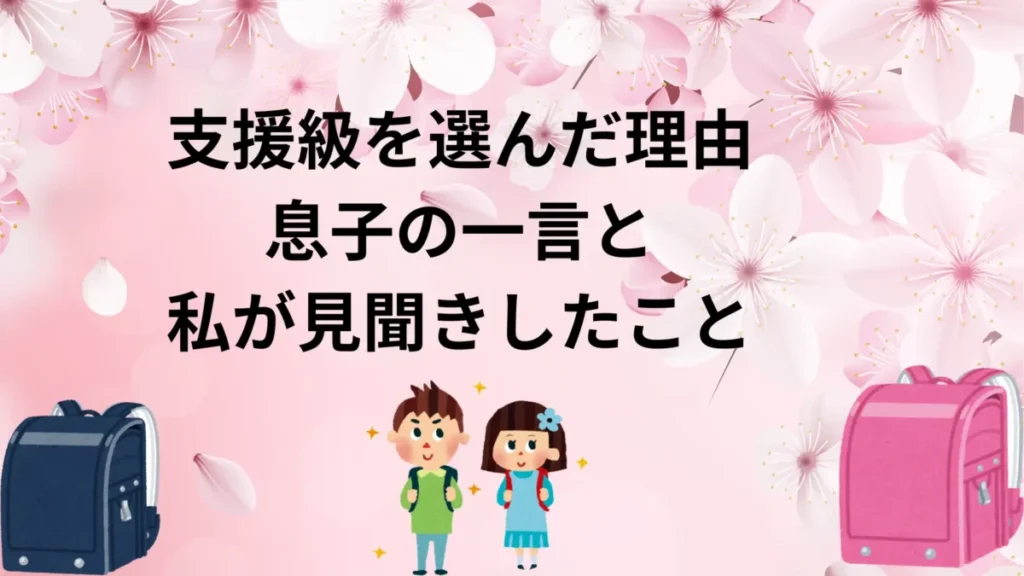就学を前に「支援学級か、通常学級か」で悩む保護者の方は少なくありません。
私もその一人でした。
今回は、私が息子の就学にあたり「支援学級」を選んだ理由、そしてその背景にあった迷いや決断についてお伝えします。
作業療法士として子どもの発達に関わってきた経験、そして母としての直感や気づき──その両方を交えた、ひとつのリアルな選択の記録です。
<この記事がおすすめの人>
就学を控えた発達障害のあるお子さんを育てている保護者の方
療育や子育て支援に関わる支援者・専門職の方
子どもが「自然に頑張れる環境」を選びました
就学を前に「支援学級か、通常学級か」で悩む保護者の方は多いと思います。私もその一人でした。そして我が家は、「支援学級」を選びました。
それは、「頑張らなければ過ごせない場所」ではなく、「自然に頑張れる場所」で息子にスタートしてほしいと思ったからです。
本人の特性と感覚を大切にしたいから
支援学級を選んだ理由のひとつは、息子自身の言葉でした。
「うるさいとこだと勉強できない。」
聴覚過敏のある息子にとって、教室のざわめきはストレスになります。オープンな環境では先生の声も届きにくく、彼にとっては集中するどころか苦痛になってしまうかもしれません。
夫も当初は「通常学級でもいいのでは?」という考えでしたが、息子のこの一言がきっかけで気持ちが変わりました。「本人がそう言うなら、それが一番だよね」と、家族で気持ちが一致しました。
選択を後押しした経験や出会い
私自身、支援学級を選ぶにあたり、これまで出会ってきた子どもたちや保護者の姿が何度も頭に浮かびました。
- 登校を拒否するようになった子ども
保育園では元気だった子が、小学校では教室にいられず、母子登校が1年続いたという話を聞きました。子どもに合わない環境が、親子にとってどれだけ負担になるかを実感しました。 - 発達障害と診断された引きこもりの青年
大学でつまずき、20年近く引きこもり続けた方の話もありました。「普通」に見えても、実はずっと生きづらさを抱えていたことに誰も気づけなかったのです。 - 支援を受けながら自立して働く方
知的障害がありながらも、幼少期から支援を受け、今では一人でバスに乗って仕事に通う人の姿に「支援の力」と「本人の力」の大きさを感じました。 - 支援学級に通う子の保護者の声
「わからないまま進むより、少人数で丁寧に教えてもらえる方が安心できる」
「疲れたら戻れる教室がある」「困ったら先生に話せる」──そんな安心できる環境があることで、子どもが生き生きと過ごしている様子を教えてくれました。 - 「特別だから!」という言葉
子どもに「どうして支援学級なの?」と聞かれたとき、「特別だから!」と笑顔で返したという保護者の言葉も印象的でした。「支援学級=かわいそう」ではなく、ポジティブに伝える姿勢がとても素敵でした。 - 私自身の進路の経験
私も中学時代、成績が振るわず進学校をあきらめ、自分に合った学校に進みました。無理のない環境の中で成績も上がり、希望の大学へも進学できました。「環境を変えることは逃げではなく、力になる」──それを実感した経験が、今回の選択にもつながっています。
「その子らしく」学べる場所を選んでいい
「人生のハードルは、無理に高くしなくていい。飛べるようになったら、少しずつ上げていけばいい。」
私は、そんな思いで支援学級という選択をしました。もちろん、この選択が正解だったかどうかは、これからの息子の歩み次第です。でも、本人が安心して過ごせる場所からスタートできたことに、今は心から納得しています。
「どの学級を選ぶか」ではなく、「どんな環境でその子が生き生きできるか」が大切なのではないでしょうか。