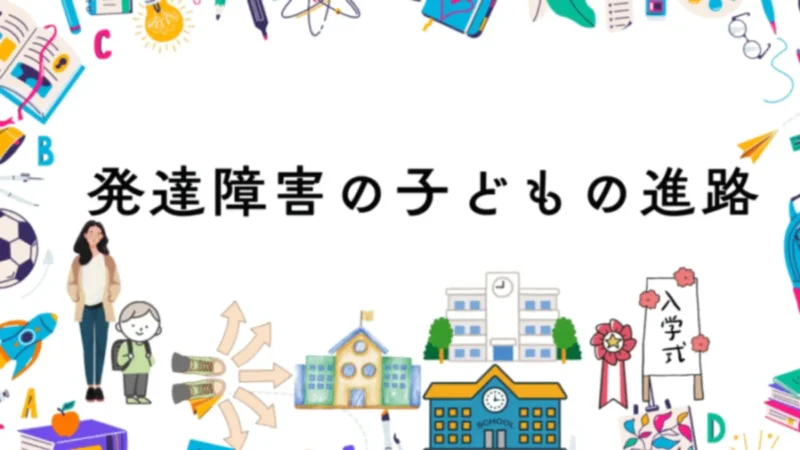発達障害の子どもが小学校に進学するときに
「支援級か通常級か、どちらがうちの子に合っているのだろう?」
「そもそも支援級ってどんな場所なの?」
そんな疑問や不安を抱える保護者の方は多いのではないでしょうか。
私自身、いざ自分の息子が小学校に進学する段階で、次々と不安や疑問が湧き上がりました。
この記事では、下の4つを詳しく紹介しています。
- 支援学級を選んだ理由
- 入学準備の具体的な流れ
- 行政とのやり取り
- 見学のポイント
少しでも「自分の子に合った学びの場はどこか」を考えるヒントになれば嬉しいです。

息子は知的障害はなく、
ワーキングメモリーが60台と極端に低いです。
WISC-Vの検査結果は他は90~110でした。
頑張れば、
普通級も可能かなと思いましたが、私たち家族は支援級を選びました。
繊細で感覚過敏があり、
大人数の集団だと疲れやすい特性があります。
なので、支援学級なら少人数で、
息子が困った時に
先生がサポートしてくれる安心感が得られると感じたからです。
<この記事はこんな方におすすめ>
・ 発達障害児の小学校進学準備で迷っている方
・支援級・通常級どちらが良いのか決めかねている方
・小学校入学に向け、相談相手を探している方
私が支援級を選んだ理由【体験談】
見学した支援学級では、先生1人に対し生徒は2人程度。
タブレットとモニターを使って個々の課題に取り組む様子を見て
「ここなら息子が安心して勉強できそうだ」と思いました。
また、かかりつけ医や作業療法士と相談した際、
「安心できる環境が息子にとって学びの力になる」
という意見をもらったこと、
さらに本人が「うるさいところだと集中できない」と話してくれたことも決め手となりました。

自閉症スペクトラムの息子は、とても不安を感じやすいです。
その不安を誰かに伝えたり、自分で処理することが難しい場合です。
また、高いところに登ったり、その場から逃げたくなり、衝動的に行動することもあり、
「なんでこんな行動をするのだろう?」という疑問には必ず本人なりの理由があります。
その理由を考え、対処する必要がありました。
息子は困ったことがあったら、ママに話してね。
ママは絶対味方でいるからねと繰り返し伝えてきました。
ですが、学校にはママはいません。
困った時に相談を誰にするか、誰にしやすいかを考えた時。
支援学級の方が相談しやすいのでは?
支援の先生もいるので、困ったら、支援学級の先生に話すんだよって。
相談相手がわかりやすくいる方が息子にとって安心できると考えました。
このような息子の性格や特性を第一に考え、支援学級が一番安心して学べる場所だと判断しました。
支援級入学までの具体的な準備とスケジュール
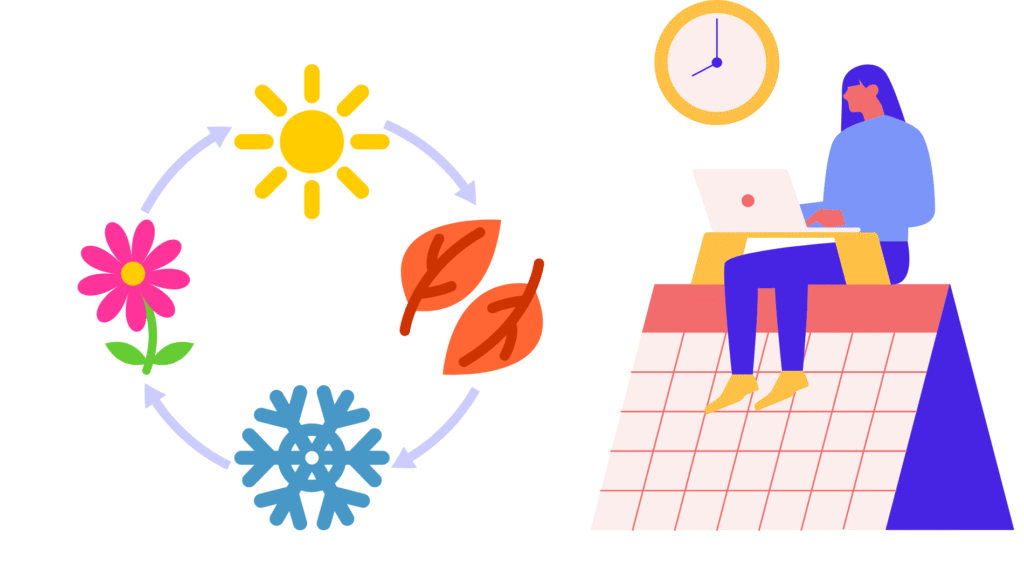
支援級入学の準備は年長の春から動き出すのが理想です。
診断書の取得、行政や学校との面談、放課後デイサービスの手配など、準備には時間がかかるからです。
*具体例*我が家の場合
- 年中3月:療育先・病院の就学前説明会に参加
- 4月~6月:福祉課・教育委員会に支援学級希望を伝え、診断書提出、学校見学、面談
- 7月~8月:WISC検査を受け、検査結果提出。放課後デイサービス見学・決定
- 9月~10月:支援級希望を教育委員会に提出。放課後デイサービスと契約、支援体制の確認
- 12月~3月:小学校の説明会、学力・身体検査、入学式の準備
入学準備をスムーズに進めるには、年長の春から支援者と連携を取り、早めの行動を心がけることが重要です。
都道府県によるとは思いますが、
教育委員会による進路の判定会が11月にあるとのことで、
私のいる県は10月までに書類や検査結果の提出でした🌞
詳しくは、各市町村にお問い合わせすることが大切です🌞
小学校入学前に知っておきたい進路の選択肢の種類
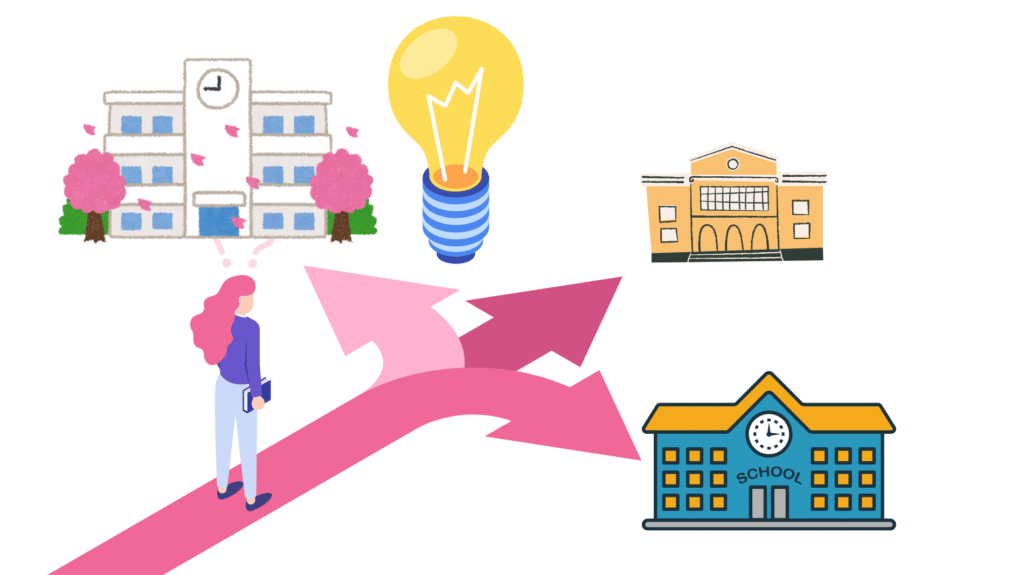
小学校の学びの場にはさまざまな選択肢があります。
子どもの特性に合った環境を選ぶことで、
学校生活がより安心で楽しいものになるからです。
通常学級
一般的な学級、1クラスは30人から40人程度です。
一年生はだいたい35人クラスを導入している都道府県が多いよ。
座席の配置や視覚教材の活用や予定表の定時など、子どもへの工夫を個別に配慮してくれることもあります。
加配制度があり、支援員を配置してくれる小学校もあります。
でも、具体的な支援内容は小学校や地域によって異なるので確認が必要になります。
なので、どんな支援が可能か学校や教育委員会に相談することが必要です。
通級指導教室
コミュニケーションや感じの読み書きの学習支援・生活向上スキルなど。
必要な子どもにはカウンセリングを受けたりすることも、
その子の特性に応じて、具体的な計画・指導がされていきます。
・自校通級
・他校通級
・巡回指導などの種類があるのです。
他校通級の場合は行っている学校まで保護者が送迎をする必要があったりするので、
働く保護者にとっては課題がある場合あります。
支援学級
学校によっては、個々のニーズに合わせて自立や社会参加を目指した支援があるところも。息子の行く学校は、様々な学年の子が一緒のクラスにいて、支援級にいる時間は国語と算数のみです。
自分の課題をしながら、つまずいたところを教えてくれると言われました。
教室も一クラスで、見学に行った際には、タブレットとモニターを利用して先生1人、生徒2人で行っていました。
時間帯によっては、様々な学年の子が必要な時間にその教室に来て課題をします。
その子にあった課題をしながら、先生が気にかけてくれている環境ですね。
特別支援学校
フリースクール
フリースクールでの出席認定は文部科学省が定めていて、手順を踏めば、出席扱いになります。
中学生とかになると出席日数が進学先に影響することもあるのでね。
まずは、フリースクールに相談して同時に、在籍校や教育委員会に連絡・相談をすることが大切
必要書類も学校や教育委員会から送られてくるものがあるから、それを提出すると出席日数に加算されます。
選択肢の内容をしっかり理解し、学校・支援者と相談しながら、子どもにとってベストな環境を選びましょう。
発達障害の子どもの進路 小学校と未来を考える
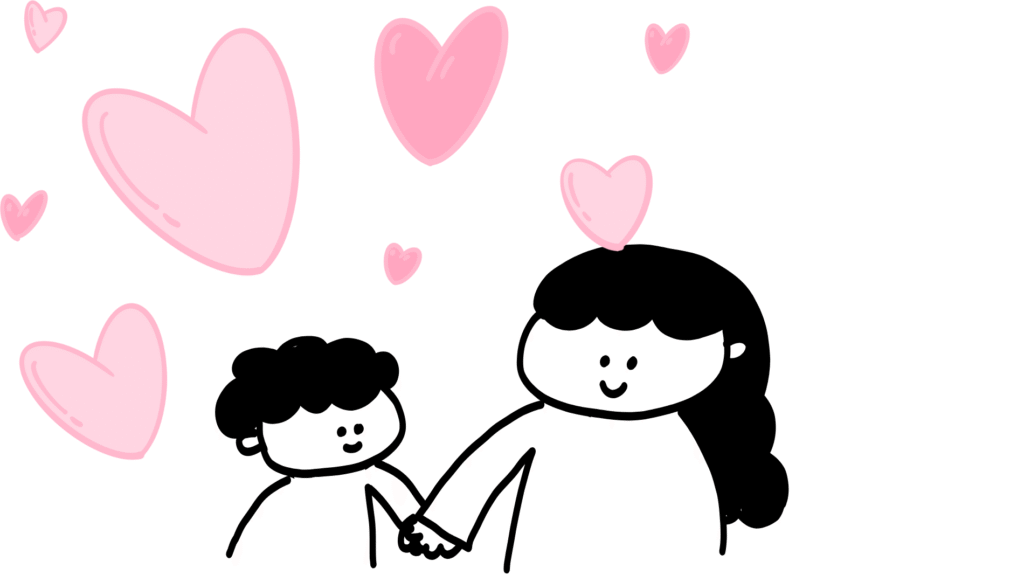
小学校進学はゴールではなく、成長に応じて進路は変わっていくものです。
支援級から通常級、通常級から支援級への移行は手続きをすれば可能であり、義務教育後の進路も多様だからです。
高校、専門学校、大学、就労支援、一般就職など、義務教育後の道はたくさんあります。
今の選択が未来を固定するわけではありません。
親として、今の選択に縛られすぎず、柔軟な気持ちで子どもと一緒に歩んでいく姿勢が大切です。
リハビリに来る子達もそれぞれのペースで、担当ではない子でも成長しているのが、はたから見てもわかります。
これからの未来は誰にもわかりませんので、思いつめすぎないようにしていきましょう。
作業療法士として
支援学級か通常級かどうしたらいいか。それは息子が息子らしく過ごせる場所を提供した方がいいと思いました。
通常級でも上手くやっていけるかもしれない。だけど、それは息子が自分を抑えこむ必要でてくる。
集団行動という自分が苦手な環境で常に生活をしなくてはならない状況はとてもつらい。
作業療法士は、身体的なコトや精神的なコト以外にも環境を考えます。
人的環境や物的環境などその人が置かれている背景も大切にします。
環境でその人の行動や過ごしやすさ、気持ちなど様々なことが影響することを知っているからです。
だから、息子が息子らしく過ごせる可能性が高い方 支援級の方が精神的に安定して過ごせると考えました。
まとめ:子どもと一緒に笑顔で進学を迎えるために

発達障害と診断され、間もない方もいるでしょう。親の気持ちが不安定な中で、進路を決めるのはとても大変で、苦しいことです。
でも、無理をせず、周りの支援者(療育先、相談員、かかりつけ医、作業療法士など)を頼り、一歩ずつ進めていきましょう。
小学校生活は長い時間があります。今支援級を選んでも、通常級に移ることは可能ですし、その逆もあります。
そのときそのときで、子どもが安心して学べる場所を柔軟に選べると良いと私は思います。
発達障害の子どもたちとその家族が、より笑顔で過ごせる時間が増えることを心から願っています。