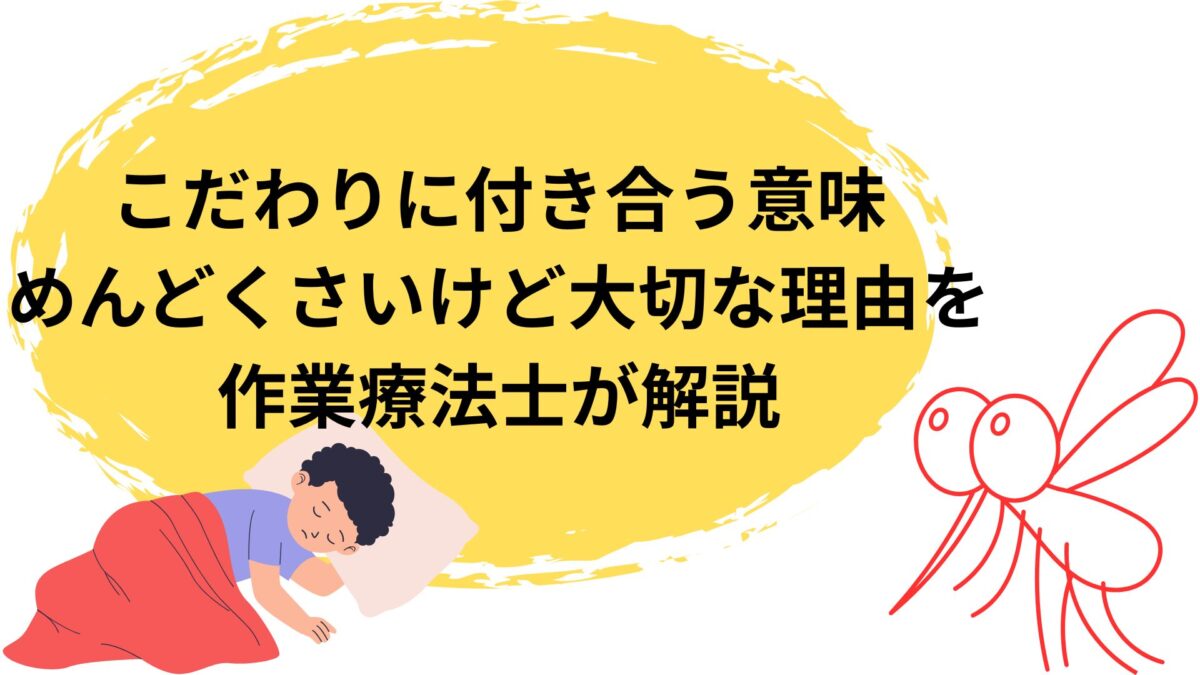めんどくさいことほど、思い出になる
「暑いよ」「蚊が出るよ」「寝れないよ」
そう説明しても、息子は首を横に振って言いました。
――「テントがいいの。」
その瞬間、私は悟りました。
(あぁ、もう聞く耳を持たない“こだわりモード”だ…)
だから私は観念して、真夏の夕方、ベランダにテントを広げました。
子どもの“やりたい”に付き合う意味
テントを張り終えると、息子は満面の笑みで叫びました。
「わぁ、ほんとにキャンプだ!」
(母にとっては、ベランダサウナと蚊との戦いなんですけどね。)
でも、こうして子どもの“やりたい”に全力で付き合う時間は、自己肯定感を育てるうえでとても大切だと感じます。
作業療法士としても、「自分の希望を尊重された」という体験は、子どもの自信や安心感につながると考えています。
真夏のベランダキャンプは予想通りの地獄だった
夜、テントの中は蒸し風呂状態。
そして、ぷ〜ん……嫌な音が。
「……蚊だ。」
私は必死にスプレーを振り、手で叩き、汗だくで戦いました。
(この必死さ、なんか方向性を間違ってない?)
でも、横で眠る息子は汗だくでもぐっすり。
その寝顔だけが、私に「やってよかった」と思わせました。
午前2時、予想通りの結末がやってくる
午前2時――。
「ママ、暑い……お風呂入りたい。」
「でしょうね‼言うと思ってたよ!」
結局、真夜中の風呂タイムの後、涼しい部屋で就寝。
テントの夜は、5時間で終わりました。がんばりました。
“めんどくささ”が親子の宝物になる
5時間のベランダテント。
母にとっては汗と蚊との戦い。
でも、寝息を立てる息子を見ながら思いました。
――この“めんどくささ”が、きっと親子の宝物になる。
だから、またいつか「テントがいいの。」と言われたら。
そのときも、きっと私は笑いながらテントを広げるでしょう。
『大事な「こだわり体験」』作業療法士の視点から。
親にとっては“ただのめんどくさい出来事”も、
子どもにとっては“かけがえのない思い出”になる。
真夏の夜、ベランダでテントを張って寝たいと言い張る息子に、私は折れた。
そして案の定、汗だくで蚊と戦い、真夜中には「暑いからお風呂」と言われるオチつき。
――普通なら「やっぱりやらなきゃよかった」で終わる話だ。
でも、作業療法士として少し冷静に考えると、これには子どもの成長に大事なポイントが詰まっている。
①「やりたい」を実現できる経験は、自己効力感を育てる
「テントで寝たい!」というこだわりを叶えられた経験は、
子どもにとって**「自分の気持ちを大事にしてもらえた」という成功体験**になる。
これは自己効力感(自分はできる、やっていいんだという感覚)を育てる大切なステップ。
②「実際にやってみて、失敗を体感する」は社会性の学習
理屈で説明されるより、実際にやってみて「暑い…蚊がいる…」と
実感した方が、「状況を予測する力」や「次に活かす学習」につながる。
次に同じことをするとき、きっと息子は「夏じゃなくて秋がいいかも」と考えるだろう。
これは「計画力」や「問題解決能力」の芽になる。
③「一緒に苦労を共有する」ことは愛着形成にプラス
一緒に汗だくになり、真夜中にお風呂に入り直したこの体験は、
子どもにとって「ママは自分に全力で付き合ってくれた」という安心感を残す。
愛着は、将来的な自己肯定感や社会性に大きな影響を与える。
テントの夜は、私にとっては“ただのめんどくさい夜”だった。
でも、子どもにとっては「ママと一緒にキャンプした楽しい夜」だ。
そしてそれは、
「自分のやりたいことを応援してくれた大人がいた」という思い出になる。
だから、たまにはめんどくささに全力で付き合うのも悪くない――
そう、作業療法士としても、母としても思うのだ。
✅ まとめ
親にとっては“ただのめんどくさい出来事”も、
子どもにとっては“かけがえのない思い出”になる。
だから、たまには全力で付き合ってあげたい。
子どもの“やりたい”を尊重することは、自己肯定感を育てるから、
夏のベランダキャンプで学んだ親子の時間の大切さ。
めんどくささを笑って受け止めれば、それが宝物になる