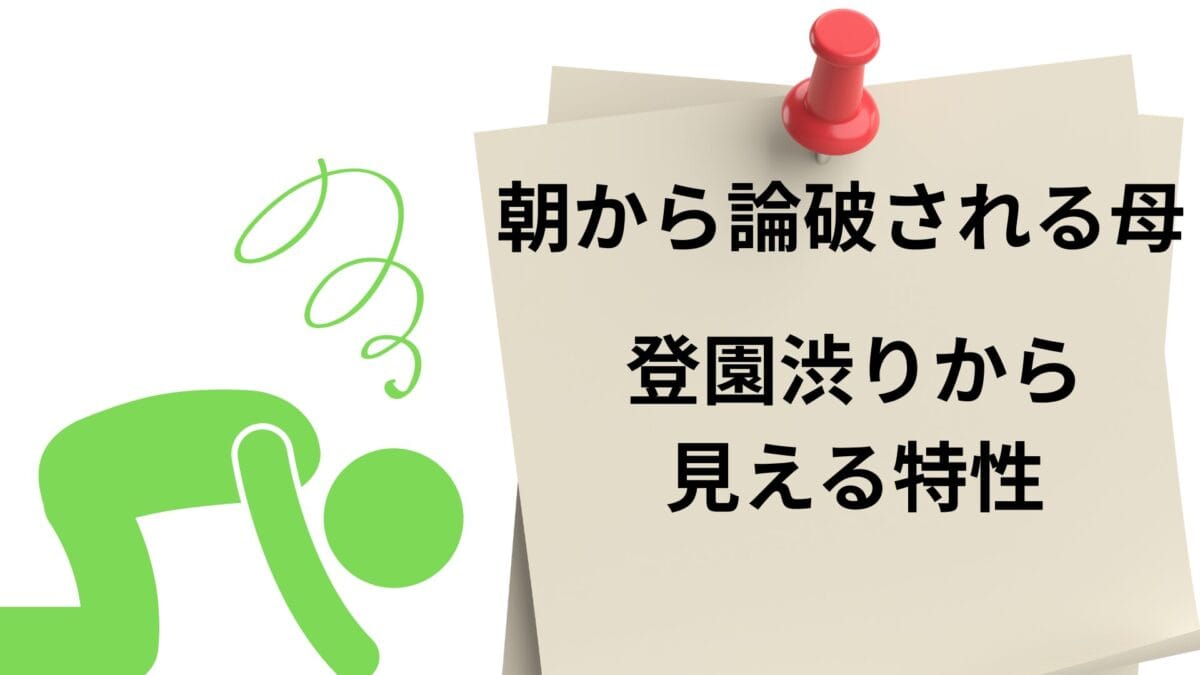「ママ、パパが働いてるから大丈夫だよ」
5歳の息子の登園渋りで始まる、我が家の慌ただしい朝。
作業療法士として15年働いてきた私でも、我が子の登園しぶりには毎朝手こずっています。
今回は、息子のやりとりから見える発達特性と、それに合った具体的な対応方法について、OTの視点で解説します。
◆ 子どもの特性を理解し、「親の工夫」で朝の余裕をつくろう
子どもが動かない原因を「困った」ではなく、「どうしたら動けるか」と考える。
これが、私たちOTの視点であり、親としてできる最も効果的な支援だと感じています。
毎朝の登園渋り、うんざりする気持ちはとてもよくわかります。
でも、特性を知ることで、関わり方を変えていくことはできるんです。
今日もうまくいかない朝があったとしても、
「子どもが動ける関わり方」を一緒に少しずつ探っていきましょう。
◆ 息子には“こだわり”や“見通しの不安”という特性がある
わが家の息子は、論理的に筋が通らないと動けないタイプ。
感情よりも「理由」で納得したい傾向があり、矛盾や曖昧さに敏感です。
また、朝のような「切り替え」が求められる場面では、見通しの立たない不安から動き出せないことが多く見られます。
こういった傾向は、自閉症スペクトラム(ASD)やADHDの特性としてもよく見られます。
◆ 朝のやりとりと、作業療法士としての支援アイデア
【朝のリアルな会話】
「ママが仕事行かないと生活できないんだよ」
「パパが働いてるから大丈夫だよ」
「ママも働かないと遠くに遊びに行けなくなるよ」
「こないだ行ったし」
「あれはママがお昼代とか遊ぶお金をパパに渡しているんだよ」
「お金を貸し借りしちゃダメって言ってたじゃん!」
「家族だからね。一緒の家計だからいいんだよ。」
「家族ならいいなら僕にもお金貸して」
……会話が、全然終わらない。
はい、正直うんざりです(笑)。
見える化とルーティン化
抽象的な説明より、「見える形」で伝えるほうが、理解が進みやすくなります。
- 朝の支度ボード(写真やイラストで一連の流れを表示)
- 「ママが働くとできることリスト」を子どもと一緒に作る
「納得」より「選択」
YES/NOで詰まる会話ではなく、選択肢を与えるとスムーズ。
- 「今日はこっちの道にする??それともあっちの道にする?」など
【行動のきっかけづくり】
行動にうつるための「楽しいスイッチ」を取り入れる。
- 好きな音楽を流す
- 車に行ったら1枚シールが貼れる仕組み
🧠 作業療法士15年目はこうみている特性分析
① 「納得しないと動けない」=こだわりの強さ・見通しの不安(ASDの特性)
- 抽象的な説明では納得できず、論理的に筋が通らないと受け入れない様子があります。
- 「お金を貸すのはだめって言ったじゃん!」と、一貫性やルールへのこだわりも見られます。
- また、「説明→納得→行動」の順序が必要で、感情では動かず、理由が必要なタイプです。
② 言葉でのやりとりが高度すぎるほど可能=言語能力が高く、発達の凹凸あり
- 年齢の割に言語理解力・記憶力・論理的思考力が高いです。
- 一方で、感情の折り合いをつける力や切り替えの柔軟さがまだ発達途中。
③ 朝の切り替えの難しさ=ADHDまたはASD特性の“行動開始の困難さ”
- 朝という「時間に追われる」「切り替えを要する」場面は特性のある子にとって苦手の代表です。
👩⚕️ 作業療法士としての対応・支援提案
1. 論理的な説明ではなく「見える化」+ルーティン化を
- 「ママが働かないと○○できない」のような抽象的説明ではなく、
図や写真・チャートを使った見える説明が有効です。 - 例えば:
- 「ママが働いたらできることリスト」や「お金のながれ」の図解
- 朝の流れを絵や写真で並べた「朝の支度ボード」
2. 「納得しないと動けない」には、“前提を共有する習慣”を
- 会話の最初に「いま何のための話なのか」「このあとどうなるか」など、
話のゴールと背景を明示することで理解しやすくなります。- 例:「今から保育園に行く準備の話をするね。遊びに行けるための大事な準備だよ。」
3. 切り替えや行動開始を楽にする「ブリッジアイテム」や「マイルール」
-
- お気に入りのぬいぐるみと一緒に車へ向かう
- 支度ができたらステッカー1枚貼れる仕組み
- 「出発5分前チャイム」や「車に行く道だけ好きな音楽をかける」など、楽しい導入スイッチを取り入れる
4. 「会話バトル」を避けるために“選択肢”を準備
- 抽象的な交渉になりそうなときは、「YES/NO」ではなく、「AかBか」の二者選択形式に。
- 例:「保育園に行くのに、こっちの道で行く?あっちの道で行く?
📝 最後に:自分の気持ちも大事に
息子さんの論理的な反論に、「ははは……もういいわ😇」となってしまう日もあります。
正直白目をむいている日もあります。
支援の原則は、
子どもを変えることではなく、関わり方と環境を変えること。
登園渋りのやりとりが少しでも楽になるよう、
「根気のいらない工夫」を重ねていけるように頑張ります🌸