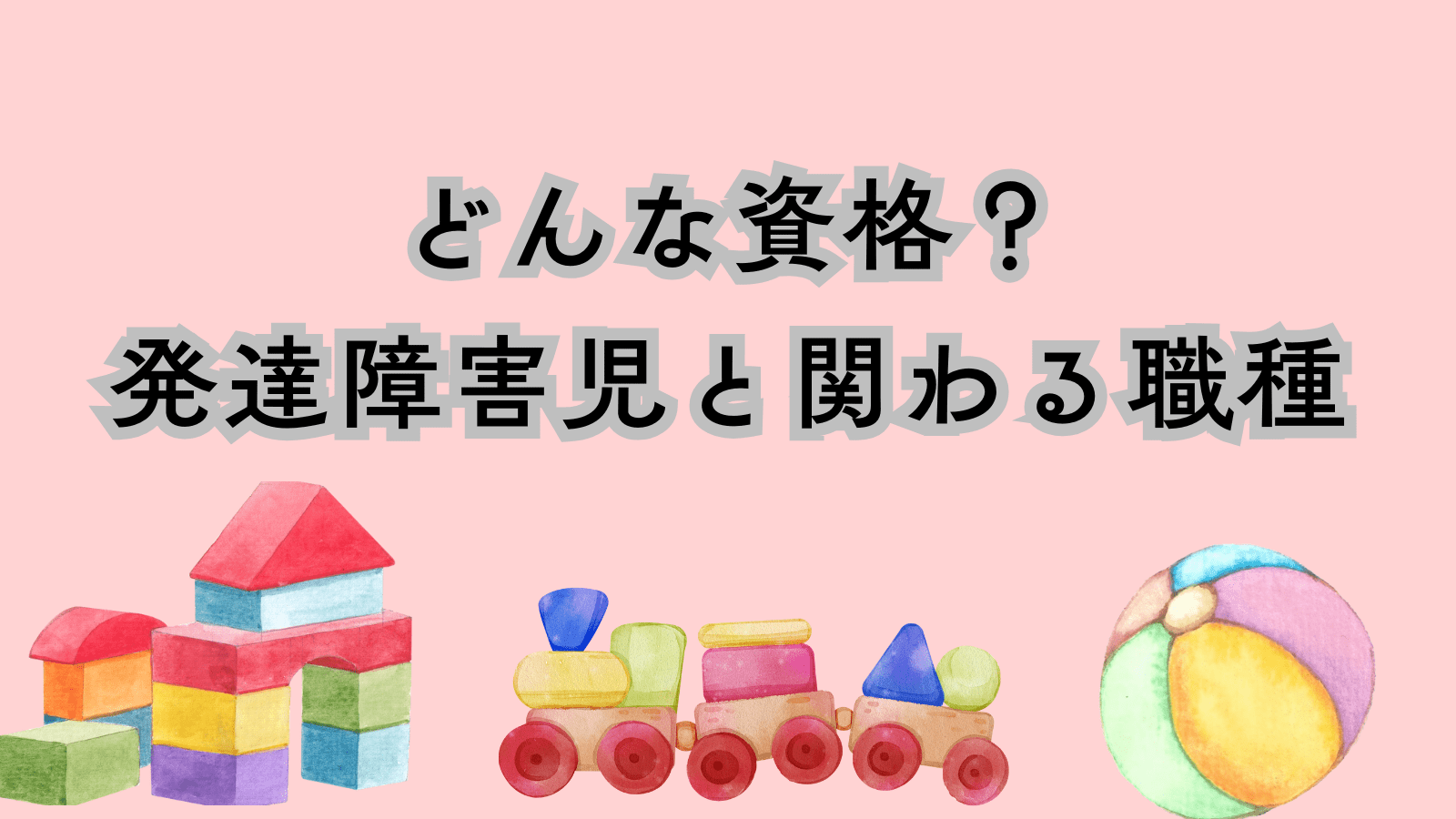療育センターや放課後デイサービスにいるこの職員さんはどんな仕事なんだろう。
何を支援してくれる人なのかな?と考えたことはありませんか?
私は、15年作業療法士をしていましたが、
息子が発達障害児と言われてから色々な専門職の人と関わりを持ちました。

「この保育士さんは普段いっている保育園の保育士さんと何が違うのかな?」と考えました。
ここでは、発達障害の子どもが関わるであろう専門職について記載をしています。
この記事を読めば、この職員さんはこんな役割なのね。
では、こんなことを相談してみようと職種の特徴に合わせた相談がしやすくなります。
この記事がおすすめの人
・療育、放課後デイサービスに通っているお子さんの保護者
・障害児に関わる仕事がしたい方
・児童発達支援管理責任者・児童指導員・保育士・作業療法士・言語聴覚士・心理士・相談支援員ってどんな仕事?って思っている方

療育や放課後デイサービスなどに通うとさまざまな専門職と関わります。
児童発達支援管理責任者・児童指導員・保育士・作業療法士・言語聴覚士・心理士・相談支援員・看護師さんなどです。
各専門職ですが、保育士・作業療法士・言語聴覚士・心理士・看護師さんなどは、子供から高齢者まで関わる方がさまざまです。
発達分野でどんなことを支援してくれる人なのか分かりますので、最後までお読みください。
療育・放課後デイサービスで関わる職種
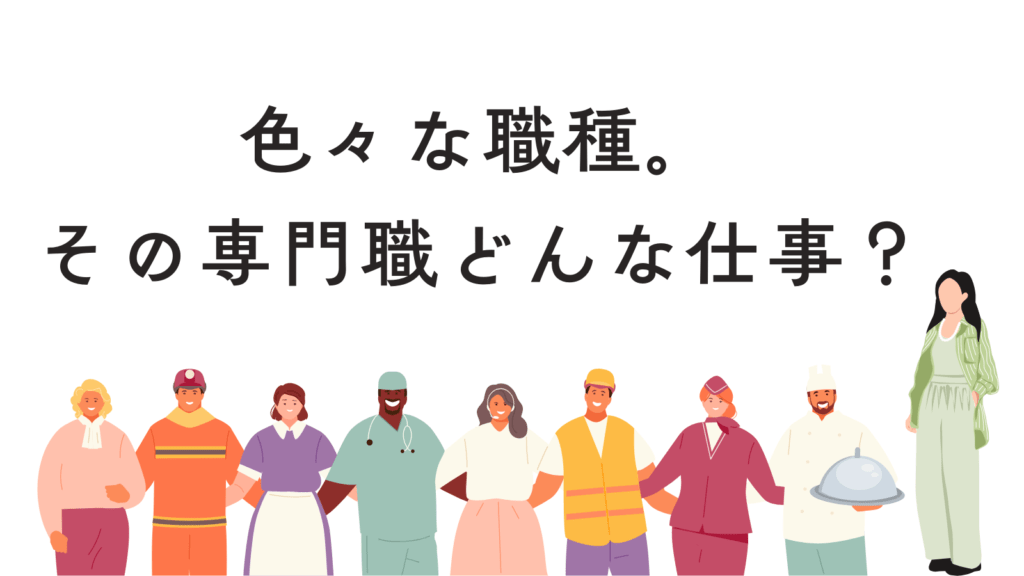
児童発達支援管理責任者・児童指導員・相談支援員・保育士・作業療法士・言語聴覚士・心理士・看護師さんなどがいます。
この方々はいったいどのような支援をしてくれて、
どのうような過程を経てこの職種になれるのでしょう。
児童発達支援管理責任者
都道府県が実施する研修の終了と実務経験があれば就くことができます。
障害のある子どもたちの支援を行う施設で、支援の作成・サービスの提供の管理を担う専門職です。
・個別支援計画の作成
子供の特性と保護者の意向をくんで作成し、
定期的に評価や修正をします。
・アセスメントとモニタリング:このもの発達
状況と課題を理解して、サービスが適切かを
確認します。
・保護者と関係機関との連携:保護者との相談
や他機関との調整を行います。
・スタッフ指導:他の職員への助言と指導も行
います。
この職種になるために
実務経験
相談支援業務・直接支援業務を5年以上経験しうち3年は障害児支援に特化していること。
国家資格を持つ場合は5年以上の従事期間が必要です。
必要な研修
基礎研修⇒実務経験が3年以上で受講が可能。
実践研修⇒基礎研修終了後、原則2年のOJT期間(教育訓練)を経て受講。
更新研修
資格取得後も5年ごとに更新研修を受講し、継続的な実務経験が求められます。
この資格は都道府県により条件に細かな違いがあるので、自治体に確認が必要になります。

保育士や社会福祉主事任用資格・訪問介護員2級以上・児童士押印任用資格等の資格保有者は実務経験が短縮されることがありますが、
高齢者福祉の分野で働いていた経験はカウントされません
児童指導員
子供たちの生活支援や成長をサポートする専門職です。
子供の生活指導や療育支援・生活指導や支援計画の立案・保護者や学校・児童相談所との連携などが仕事になります。
児童福祉法や管理制度の理解・放課後デイサービスや児童館の運営などの
児童福祉の基礎知識や子供の発達段階の理解・障害のある子どもの配慮をする。
子どもの理解・その発達段階に応じた支援と生活面での指導を研修として学び。
他にも保護者や学校との連携をしていきます。
児童支援員になるために
福祉施設教員養成校を卒業・大学、大学院で社会福祉学、心理学、教育学、社会学を専攻。
社会福祉士・精神保健福祉士の資格取得者
高校卒業後2年以上児童福祉事業に従事。
教員免許を取得後、適正を都道府県知事が認められた場合になれます。
相談支援専門員
発達障害児とその家族が自立した生活が送れるように必要なサービスを調整・支援の計画を作成する専門職です
支援計画を作成や家族や本人からの相談にのり、助言や情報提供を行います。
また、学校や医療機関と連絡を行い包括的な支援ができるように連携をします
相談員になるために
資格を取得するためには、障害児相談支援事業や児童福祉施設での実務経験が3~10年ほど必要です。
都道府県が実施する相談支援受持者初任者研修を修了すると資格は得られますが、
5年以内に相談支援従事者現任研修を受講する必要があります。
また更新制で5年ごとに現任研修を受講する必要があります。
国家資格保有者
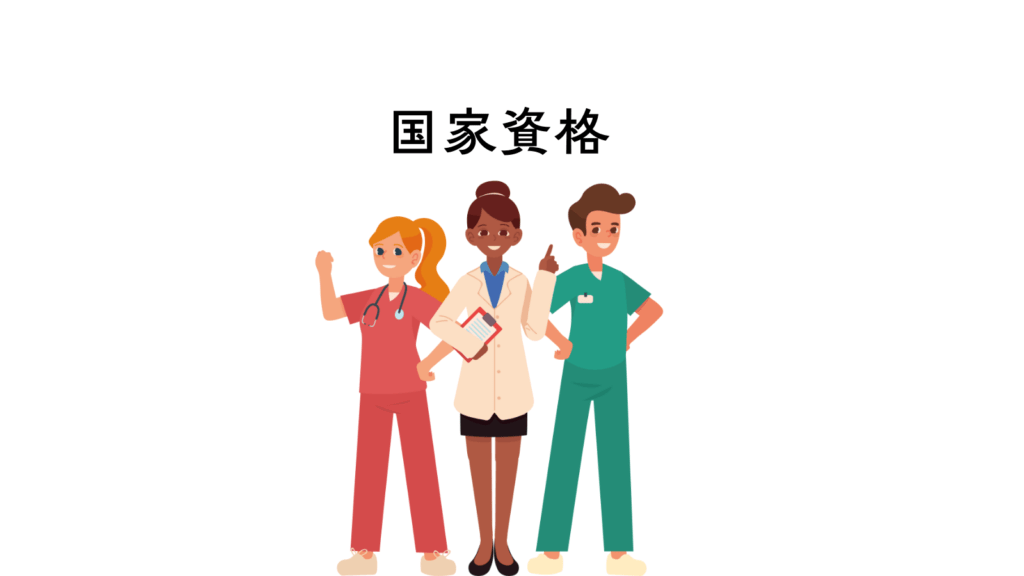
保育士・作業療法士・言語聴覚士・心理士・看護師は国で指定された試験を受ける必要がある国家資格となります。
保育士
乳幼児から小学校入学前の子供の保育と保護者への指導を行います。
主に発達障害児の特性や子供からの見え方の理解や
合理的配慮など制度に基づく支援・子供の発達状態に応じた支援や
集団生活での適応に重きを置いた支援です。
発達障害児と関わる保育士は、通常の保育の知識に加え、研修を受けている場合が多いです。
各都道府県主催の研修や厚生労働省が定める基準に基づいた研修、「子育て支援員専門研修」があります。
オンラインでの保育士等のキャリアアップ研修もあります。

日本福祉大学や国立リハビリテーションセンターでは働きながらまたは、7ヵ月という期間で学べるカリキュラムがあります
保育士になるために
厚生労働省が指定する大学・短期大学・専門学校などで所定の課程を修了すると保育士資格が得られます。
また、保育士試験を受験して合格すると保育士として働けます。
受験資格は
・大学・短期大学・専門学校卒業
・高卒以上(平成3年3月31日以前に卒業をしている場合)
・平成3年4月1日以降に高校を卒業した場合は実務経験が
児童福祉施設で2年以上かつ2880時間以上の勤務実態があれば、受験資格を得られます。
・中卒:児童福祉施設で5年以上かつ7200時間以上の実務経験。
作業療法士
身体や心に障害がある人を対象に生活を支援するリハビリの専門職です。
「その人らしい生活を大切にしながら多角的な支援を行う職業です。
発達障害児と関わる作業療法士は、
子どもの発達と日常生活の質の向上のために支援を行います。
具体的には感覚統合や課題志向型アプローチ・ペアレントトレーニングなど
科学的根拠に基づき、それぞれに適したものを提供していきます。
また、日常生活動作・社会性やコミュニケーションスキルの向上
・発達の促進・環境調整と道具の提案・そして保護者への支援です。
作業療法士になるために
文部科学省・厚生労働省が指定する養成学校にて3~4年学び、国家試験を受け資格を習得します。
発達分野で働く作業療法士の割合は正確な割合はでていませんが、
非常にすくないのが現状です。全体の1%未満とも言われています。
言語聴覚士
話す・聞く・食べるに関する問題を支援する専門職で、
言語・コミュニケーションの回旋や聴覚障害への対応
・嚥下障害の訓練・言語発達の支援に関わります。
発達分野では、言葉の遅れや構音障害・吃音を有する子供に対して、
コミュニケーション能力の向上や言語発達支援で関わることが多いです。
アプローチとしては個別セラピー・プレイベースアプローチ・社会的スキル訓練・絵カードや視覚支援ツールなどがあり、個々の支援内容により異なります。
言語聴覚士になるために
高校卒業後は3~4年生の養成学校へ進学をし、
国家資格の受験資格を取得後国家試験に合格する必要があります。
大学卒業後は1~2年生の課程を修了する場合もあります。
心理士
心や発達に問題を抱える人々を支援することです。
臨床心理士・臨床発達心理士・公認心理師などがあり、
それぞれの専門性に応じて対応をしています。
発達分野における心理士は発達課題を抱えている人に対して、
発達の状況や社会的な適応の困難さを評価し、
個別のニーズに合わせて支援プランを作成・療育やカウンセリングを提供します。
また、家族に置いても子供の特性に合わせた対応方法や不安・育児ストレスを軽減するためのサポートを行います。
心理士になるためには
心理士になるためには、目指す心理士によって過程が異なります。
臨床心理士:大学院修了し試験に合格する必要があります。
活躍分野は医療や教育・福祉です。
また、心理士の資格は5年等の定期的な更新が必要ものが多いです。
公認心理師:大学・大学院卒業、
または実務経験を積み試験に合格する必要があり、
医療・教育・司法での活躍ができます
臨床発達心理士:発達心理学を基盤に不登校や虐待・発達障害などの課題を抱える人々を支援します。
受験資格を満たした後書類審査と筆記試験・面接にて口述試験を受けることで資格が得られます。
心理士の中では公認心理師が国家資格で、他は民間資格です。
看護師
発達分野でできること
睡眠や身体状況、子どもの周りの対人関係状況を確認しながら
心理的身体的な健康状態を確認していきます。
体調面・表情や言動・感情の表現・行動・生活リズムなどを観察し、
評価しながら支援し看護計画を作成します。
看護計画に基づいて、子どもの健康管理や将来を見据えた療育の支援を提供します。
また、家族との連携も大切で、
子どもの状態やケアの内容を家族と統一することも大切で、
セルフケア能力においては、生活上でできていること難しいことを確認しながら
本人の特性を考えながら支援計画を修正立案します。
看護師になるために
高卒者の場合は3~4年の看護士の教育課程を終了後
中卒者は5年移管の看護師養成課程高2進学
・または准看護師資格を取得後に看護師養成校に進むことで、看護師試験の受験資格を得ることができます。
毎年2月に実施される国家資格に合格すると看護師免許の取得となります。
社会人では専門学校・短期大学で学び国家資格に挑むのが最短ルートです。
どんなことを相談している?

息子が行っている療育施設は、保育士・作業療法士・相談支援専門員・児童指導員の方がいます。
児童発達支援管理責任者の方もいますが、あまり関わりがありません。
主に相談している人は相談支援専門員の方です。
この方には息子が療育施設の回数を減らしたいと訴えてきた際に相談をしました。
現場の児童指導員の方や保育士の方々に普段の様子を聞いてくれ、
回数が減らした後の対応も一緒に考えてくれました。
放課後デイサービスを検討している時にも、各施設の情報を教えていただきました。
あと息子はリハビリにも通っているので、そちらの作業療法士の方にも相談をしています。
こちらの作業療法士の方は、日常のちょっとしたことから私の悩みまで聞いてもらっています。
発語がお友達同士で聞き取りにくいことがあるみたいなので、言語療法を受けた方がいいか。
発達障害を診断された人はどんな進路を辿る人がいるのか。
姿勢を保ってられないが、何かよい方法はないかなど。
歯医者さんで寝ていられなくて、診察ができない。どこか理解がある歯医者はないかなど。
経験が多い専門職の方は、いろいろな保護者さんからいろいろな情報を得ています。
そして、保護者からの口コミ情報はハズレが少ないです。
本当は保護者同士で情報を共有できると辛い思いも最低限で済みそうですが、
なかなか難しいですよね。。
まとめ

いろいろな職種の方が連携をとり、
我が子の成長をサポートしてくれていると思うと心強いですよね。
でも、この職種の方々はお子さんだけのサポートではなく、
親御さんのサポートもしてくれます。
ちょっと忙しそうだなとか。
なかなか相談できないなどもあるかもしれませんが、
勇気を出して相談してみましょう😆